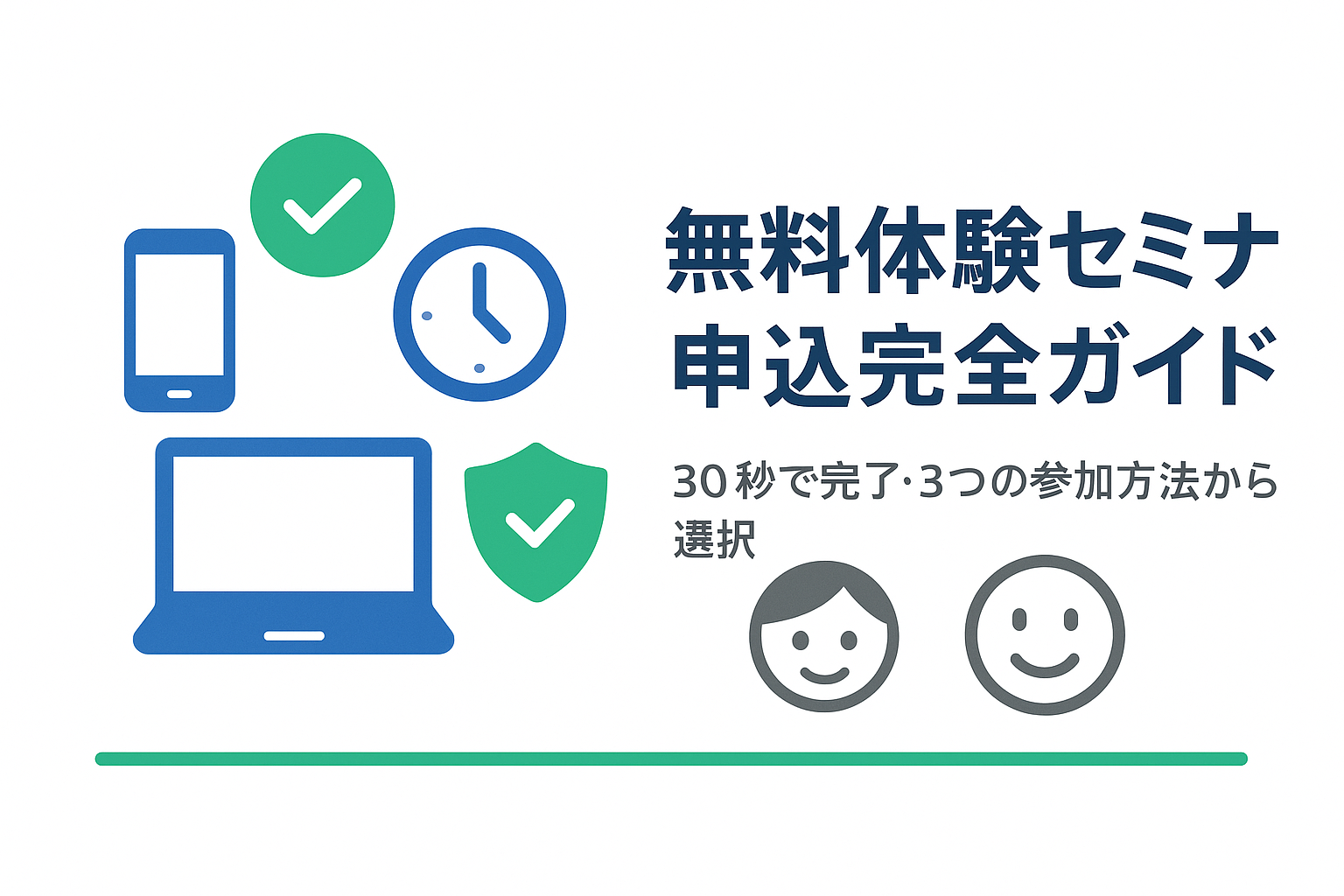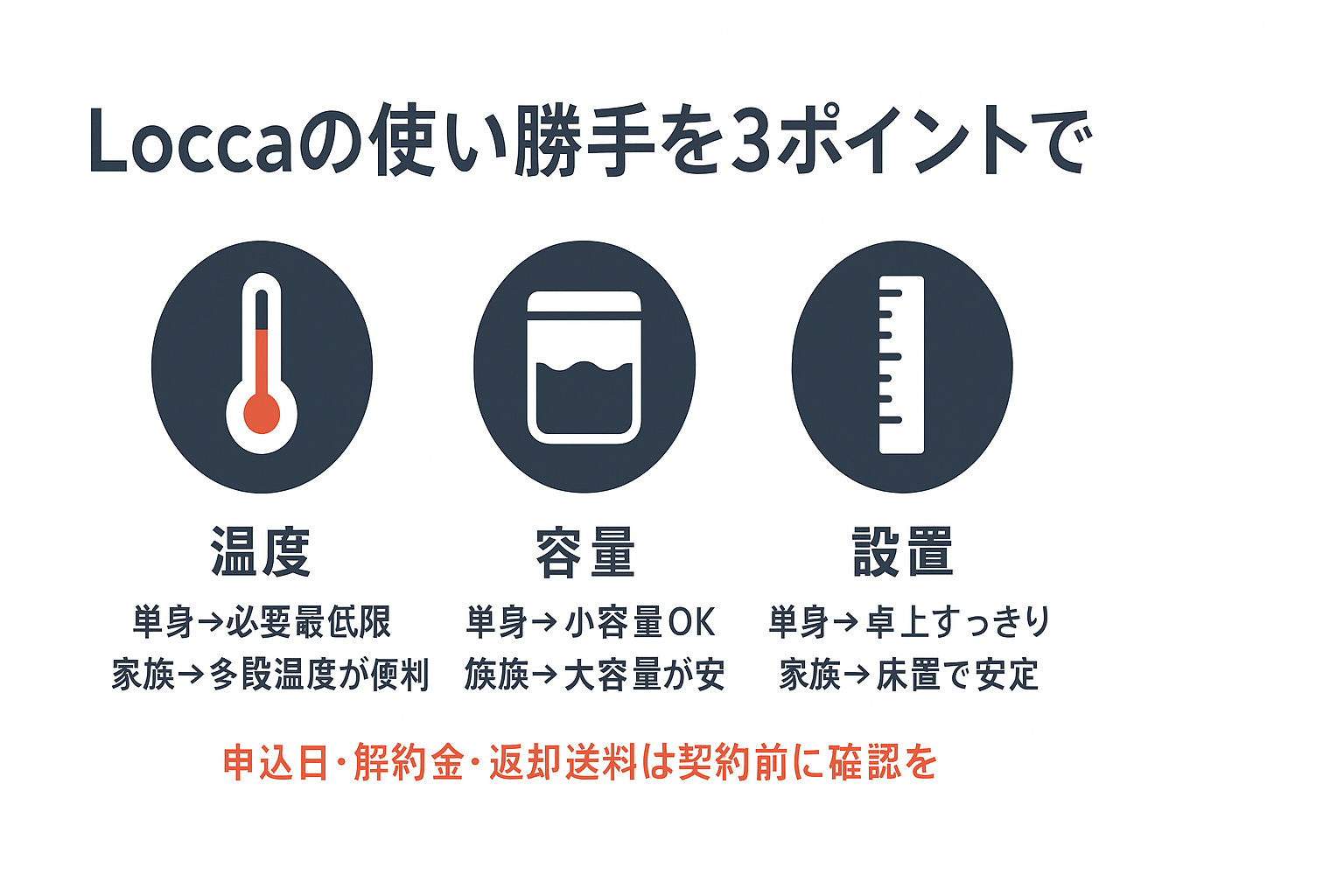子育てママのプログラミング学習継続術【挫折しても大丈夫!現実的な両立方法】

「プログラミングを始めたけど、全然進まない…」「子どもの世話で学習が中断ばかり」「このままだと挫折してしまいそう」
そんな風に思っているママ、本当にお疲れさまです。そして安心してください。あなたは決して一人じゃありません。
実は、プログラミング学習の挫折率は約90%と言われていて、子育て中のママなら尚更、継続するのは本当に大変なことなんです。私も何度も「もうダメかも…」と思った経験があります。
でも大丈夫。挫折しそうになっても、一時的に学習が止まっても、また再開すればいいんです。完璧を目指さなくても、小さな一歩を積み重ねれば、必ず前に進めます。
この記事では、子育てと両立しながらプログラミング学習を継続するための、現実的で無理のない方法をお伝えします。理想論ではなく、実際に多くのママが実践している等身大の継続術です。
めちゃくちゃ長くなってしまったので、目次から興味あるところだけ読んでください!w
サイトをブックマークしてまた挫折しそうになったら、読みにきてくださいね。
まずは現実を受け入れよう:挫折は当たり前のプロセス
プログラミング学習の厳しい現実
最初に正直にお話しします。プログラミング学習で挫折を経験するのは、決して珍しいことではありません。
挫折率のデータ:
- プログラミング学習者の約87.5%が挫折経験あり
- 独学者の挫折率は特に高く、約6割
- 主な挫折理由:「不明点を聞ける環境がなかった」「エラーが解決できない」「モチベーションが続かない」
これらの数字を見て、「やっぱり私には無理なのかな…」と思いました?でも違うんです。
むしろ、これだけ多くの人が同じような悩みを抱えているということは、あなたの感じている困難は「当然のプロセス」だということなんです。
子育て中のママが抱える特有の困難
一般的な学習者に加えて、子育て中のママにはさらに特別な制約があります:
時間的制約 – 子どもの世話、家事、急な発熱やぐずりなど、予定通りにいかないのが日常です。「今日は2時間勉強するぞ!」と思っても、子どもが熱を出したらそれどころではありませんよね。
精神的負担 – 学習が進まないと「私って能力がないのかな」「他のママはもっとうまくやってるのかな」と自分を責めてしまいがち。でも、それは決してあなたが悪いわけではありません。
孤独感 – プログラミング学習は基本的に一人で進めるものなので、つまずいた時に相談できる人がいないと、どんどん孤独になってしまいます。
これらの困難は、子育て中のママなら誰でも経験することです。だからこそ、一般的な学習方法ではなく、ママの現実に合わせた継続方法が必要なんです。
完璧主義からの脱却が継続のカギ
継続できないママの多くに共通するのが「完璧主義」です。
「毎日必ず勉強しなければ」「理解できないところがあったら先に進んじゃダメ」「他の人と比べて遅れている」
こんな風に思っていませんか?でも、子育て中にそんな完璧を求めるのは現実的じゃありません。
新しい考え方:
- 毎日できなくても大丈夫
- 70%理解したら次に進んでOK
- 他人と比較する必要なし
- 一時停止も立派な戦略の一つ
この考え方に変えるだけで、学習に対するプレッシャーがぐっと軽くなって、継続しやすくなります。
15分継続法:子育て中でも実践可能な超細分化学習
なぜ15分なのか?
子育て中のママにとって、まとまった時間を確保するのは至難の業です。でも、15分なら意外と見つけられるものです。
15分で何ができるの?
- HTML基礎タグの学習と練習
- CSS一つのプロパティの理解と実践
- JavaScriptの短いコード書きと動作確認
- エラーの解決策をググって試行
- 前日の復習とコードの見直し
「たった15分で意味があるの?」と思うかもしれませんが、実は学習において「継続性」は「時間の長さ」よりもずっと重要なんです。
15分学習の実践方法
準備段階: まずは15分で何を学習するか、前もって決めておきます。その日の朝、コーヒーを飲みながら「今日はCSSのフレックスボックスを15分だけやろう」と決める程度でOKです。
実践例:月曜日の場合
- 0-5分:前回の内容を軽く復習
- 5-12分:新しい内容の学習(今日はflex-directionについて)
- 12-15分:実際にコードを書いて動作確認
実践例:水曜日の場合
- 0-10分:昨日エラーで止まったコードの修正を試す
- 10-15分:解決できたら次に進む、できなかったら解決方法をメモして終了
このように、その日の状況に応じて柔軟に内容を調整します。重要なのは「15分間、プログラミングに向き合った」という事実です。
15分学習を支える工夫
環境づくり – パソコンをすぐに開ける状態にしておく。教材も開きやすいところにブックマーク。準備時間を短縮することで、実際の学習時間を最大化できます。
記録をつける – 学習したことを簡単にメモする習慣をつけましょう。「今日はHTMLのtableタグを学習、明日はCSSでスタイリング予定」程度の簡単なもので十分です。
家族への説明 – 「今から15分だけお勉強するね」と家族に伝えておく。時間を区切ることで、家族も協力しやすくなります。
挫折リカバリー術:一時停止から学習再開までの道筋
挫折=失敗ではなく「一時停止」
学習が止まってしまった時、多くの人は「挫折した」「失敗した」と考えがちです。でも、子育て中のママにとって、学習が止まるのは当たり前のこと。それを「一時停止」と捉え直してみてください。
一時停止が起こる理由:
- 子どもの体調不良や行事で忙しくなった
- 仕事や家庭の事情で時間が取れなくなった
- 難しいところでつまずいて、やる気が下がった
- 他のことに興味が移って、優先順位が変わった
どれも、ママなら誰でも経験することです。大切なのは、止まったことを責めるのではなく、「いつ再開するか」を考えることです。
学習再開の3ステップ
Step 1: 現状確認(5分) まずは、どこで止まったのかを確認します。最後に学習した内容、理解できていた部分、つまずいていた部分を思い出してみてください。完全に思い出せなくても大丈夫です。
Step 2: 再開ポイントの設定(10分) いきなり止まったところから再開するのではなく、少し前の「確実に理解できていた部分」から始めます。これは自信を回復させるためにとても重要です。
「せっかく進んだのに戻るなんて…」と思うかもしれませんが、復習することで理解が深まりますし、何より「できる」という感覚を取り戻すことができます。
Step 3: 小さな目標設定(5分) 再開の最初の目標は、とにかく小さく設定します。「今日は15分だけ」「HTMLの復習を軽く」「エラーを1個解決する」など、確実に達成できそうなものにします。
再開を成功させるコツ
完璧を求めない – 止まっていた期間のことは忘れて、今日からまた始めればいいんです。ブランクがあっても、一度学んだことは意外と覚えているものです。
周囲に宣言する – 家族や友人に「また勉強を始める」と軽く伝えておきましょう。応援してもらえるだけでなく、自分へのコミットメントにもなります。
学習仲間を見つける – 同じようにプログラミングを学ぶママ友がいると、お互いに励まし合えて再開しやすくなります。SNSやオンラインコミュニティを活用するのもおすすめです。
モチベーション維持法:小さな成功の積み重ねと見える化
小さな成功を大切にする習慣
プログラミング学習では、大きな達成感を得られるまでに時間がかかります。でも、毎日小さな成功を積み重ねることで、モチベーションを維持できます。
小さな成功の例:
- エラーを一つ解決できた時 → 「やった!一歩前進した!」
- 新しいタグの使い方を覚えた時 → 「HTMLの知識が増えた!」
- 15分の学習を3日連続でできた時 → 「継続力がついてきた!」
- コードが予想通りに動いた時 → 「プログラマーっぽいことができた!」
これらの小さな成功を見過ごさずに、しっかりと自分を褒めてあげることが大切です。他の人から見たら些細なことでも、あなたにとっては立派な成長なんです。
学習の見える化でモチベーション維持
目に見えない努力は、続けるのが難しいものです。だからこそ、学習の過程を「見える化」することが継続の助けになります。
学習記録のつけ方:
シンプルカレンダー法 – 卓上カレンダーに、学習した日にシールやマークをつけるだけ。子どもと一緒に「今日もお勉強できたね」と確認するのも楽しいものです。
学習時間累計法 – 15分×20日=300分(5時間)、30分×15日=450分(7.5時間)のように、累計時間を記録します。「もう10時間も勉強してる!」と実感できて、自信につながります。
できたことリスト法 – 学習した内容を簡単にリスト化します。「HTMLの基本タグ10個覚えた」「CSSでボックスモデル理解」など、具体的な成果を書き留めておくと、振り返った時に達成感を味わえます。
写真記録法 – 作ったWebページのスクリーンショットを保存しておきます。最初は簡単なものでも、後で見返すと「こんなこともできるようになったんだ」と成長を実感できます。
目標設定のコツ
モチベーション維持には適切な目標設定が欠かせません。ただし、子育て中のママには特別な配慮が必要です。
SMART目標の応用:
- Specific(具体的): 「プログラミングを頑張る」ではなく「HTMLとCSSでシンプルなWebページを作る」
- Measurable(測定可能): 「勉強時間月20時間」「学習日数月15日」など数値化
- Achievable(達成可能): 子育ての現実を考慮した無理のない設定
- Relevant(関連性): 在宅ワークという最終目標につながる内容
- Time-bound(期限): 「3ヶ月でHTML/CSS基礎完了」など期限設定
柔軟性を持った目標設定: 目標は設定したら変えてはいけないものではありません。子どもの成長や家庭の事情に応じて、柔軟に調整していくことが大切です。
家族巻き込み戦略:周囲を協力者に変えるコミュニケーション
パートナーの理解を得る方法
プログラミング学習を継続するために、パートナーの理解と協力は不可欠です。でも、いきなり「勉強したいから協力して」と言っても、なかなか理解してもらえないこともありますよね。
効果的な説明の仕方:
具体的なメリットを伝える – 「プログラミングができるようになると、在宅で月5-10万円稼げるようになって、子どもの教育費の足しになる」「通勤時間ゼロで、保育園のお迎えに余裕ができる」など、家族全体にとってのメリットを具体的に説明しましょう。
学習時間を明確にする – 「毎晩10時から11時までの1時間だけ」「土曜の午前中2時間だけ」など、具体的な時間を提示します。無制限に時間を使うわけではないことを伝えると、理解を得やすくなります。
協力内容を具体化する – 「その間だけ子どもを見ていてもらえる?」「夕飯の準備を代わってもらえる?」など、具体的にお願いしたいことを伝えます。曖昧なお願いよりも、明確な依頼の方が協力しやすいものです。
感謝の気持ちを表現する – 協力してもらったら、必ず「ありがとう、おかげで勉強が進んだよ」と感謝を伝えます。小さなことでも感謝されると、次も協力したくなるものです。
子どもとの両立テクニック
子どもがいると、どうしても学習が中断されがちです。でも、工夫次第で子どもと一緒に過ごしながらでも学習を進めることができます。
子どもを巻き込む学習法:
「ママのお勉強タイム」を設定 – 子どもに「ママはこれからお勉強するから、○○ちゃんも塗り絵(or読書)をしない?」と提案します。一緒に静かな時間を過ごすことで、お互いに集中できます。
プログラミングに興味を持たせる – 「ママはコンピューターと話すお勉強をしてるんだよ」「この画面に文字を書くと、Webページができるんだよ」と簡単に説明して、子どもの興味を引きます。
学習の成果を見せる – 簡単なWebページができたら、子どもに見せてあげましょう。「すごいね、ママ!」と言ってもらえると、モチベーションも上がります。
子どもの生活リズムを活用 – お昼寝の時間、夜寝た後、朝早起きしてなど、子どもの生活パターンに合わせて学習時間を設定します。
実家や友人からのサポート活用
家族だけでなく、実家の両親や友人からのサポートも活用しましょう。
実家の両親へのお願い – 月に1-2回、数時間子どもを見てもらって、集中して学習する時間を作ります。「孫と過ごせて嬉しい」と言ってもらえることも多いです。
ママ友との協力 – お互いの子どもを預かり合う「学習協力制」も効果的です。「今度の土曜日、2時間だけ○○ちゃんを預かるから、来週は逆にお願いします」という感じで。
一時保育の活用 – 月に何回か一時保育を利用して、まとまった学習時間を確保するのも一つの方法です。費用はかかりますが、投資と考えれば価値があります。
メンター活用術:専門サポートで継続力を強化
なぜメンター制度が子育てママに必要なのか
プログラミング学習でつまずく最大の理由は「分からないことを聞ける人がいない」ことです。子育て中のママは特に、一人で悩み続けることが多く、それが挫折につながってしまいます。
メンターがいることのメリット:
- エラーや不明点をすぐに解決できる
- 学習方向性を軌道修正してもらえる
- モチベーションが下がった時に励ましてもらえる
- 現実的な学習スケジュールを一緒に立ててもらえる
- 子育てとの両立について理解してもらえる
テックアカデミーのママ支援体制
数あるプログラミングスクールの中でも、テックアカデミーは特に子育て中のママに理解のあるサポート体制が整っています。
子育てママに優しいサポート内容:
週2回のメンタリング – ビデオチャットで直接メンターと話せるので、学習の悩みだけでなく、子育てとの両立についても相談できます。「今週は子どもが風邪を引いて全然勉強できませんでした」と正直に話しても、「お疲れさまです。体調が回復したら無理のないペースで再開しましょう」と理解を示してくれます。
チャットサポート(15時-23時) – 夜の時間帯もサポートしているので、子どもが寝た後の学習時間に質問できます。「エラーが出て進めません」とチャットすると、通常数分以内に回答がもらえるので、貴重な学習時間を無駄にしません。
柔軟な学習期間設定 – 4週間、8週間、12週間、16週間から選択できるので、自分の生活スタイルに合わせて無理のない期間を設定できます。「子どもが小さいからゆっくり16週間で」「ある程度時間が取れるから8週間で集中して」など、個々の事情に応じて調整可能です。
実際の受講ママの声: 「テックアカデミーのメンターは理解がある方ばかりなので、家の事情を理解した上で学習スケジュールを立ててくれたり、子育てしている人でも学習しやすいと思います。学習が思うように進まない時はメンタリングで他の案を提案してもらったり、私自身もかなり助けてもらいました」
継続をサポートする仕組み:
TechAcademyワークス – 学習完了後、実際の案件を紹介してもらえるサービスもあります。「勉強したけど、実際に仕事にするにはどうすれば?」という不安も、具体的なサポートで解消できます。
卒業生コミュニティ – 同じようにテックアカデミーで学んだママたちとつながることができます。お互いの体験談を共有したり、励まし合ったりできる貴重なコミュニティです。
メンターとの効果的な付き合い方
メンター制度を最大限活用するためのコツもお伝えします。
正直にコミュニケーション – 子育ての大変さや時間の制約について、遠慮せずに相談しましょう。メンターは多くの受講生を見てきているので、きっと理解してくれます。
事前準備をする – メンタリングの時間を有効活用するために、質問したいことや相談したいことを事前にまとめておきます。限られた時間の中で、最大限のサポートを受けることができます。
小さな進歩も報告する – 「今週は15分ずつですが、毎日学習できました」「エラーを自力で解決できました」など、小さな成果も共有しましょう。メンターも一緒に喜んでくれますし、モチベーション維持につながります。
ママコミュニティ活用:同じ境遇の仲間との励まし合い
一人じゃない安心感の力
プログラミング学習は孤独になりがちですが、同じような境遇の仲間がいると、継続力が格段に上がります。
コミュニティがもたらす効果:
- 「みんな同じように悩んでいる」という安心感
- お互いの小さな成功を喜び合える関係
- 挫折しそうな時の励ましあい
- 実践的な両立テクニックの情報交換
- 一緒に頑張る仲間がいるという連帯感
おすすめのママ向けコミュニティ
SNS(Twitter/Instagram)でのハッシュタグ活用 – #ママプログラマー #子育てプログラミング #ママエンジニア などのハッシュタグで、同じように頑張っているママたちを見つけることができます。日々の学習記録を投稿して、お互いにいいねやコメントで励まし合いましょう。
オンライン学習コミュニティ – SlackやDiscordを使った学習コミュニティに参加する方法もあります。テキストベースなので、子どもが寝た後の時間でも気軽に参加できます。
地域のママ向けプログラミング勉強会 – 最近では、子連れOKのプログラミング勉強会も各地で開催されています。実際に顔を合わせて話ができると、より深いつながりができます。
コミュニティでの効果的な活動
学習記録の共有 – 「今日はCSSのフレックスボックスを学習しました」「エラーで2時間悩みましたが、最終的に解決できました」など、日々の学習内容を共有します。他の人の頑張りを見ることで、自分も「私も頑張ろう」という気持ちになります。
困った時の相談 – 「この部分がどうしても理解できません」「子どもが熱を出して1週間勉強できませんでした…」など、困ったことや悩みを正直に相談しましょう。きっと同じような経験をした人からアドバイスやエールをもらえます。
小さな成功の報告 – 「初めてWebページが完成しました!」「エラーを一人で解決できました!」など、小さな成功も積極的に報告しましょう。みんなで喜び合うことで、成功体験がより印象深くなります。
情報交換 – 「この教材が分かりやすかったです」「こんな学習方法が効果的でした」など、実践的な情報を交換します。同じ境遇の人からの情報は、とても参考になります。
成長段階別継続戦略:子どもの年齢に応じた学習調整法
乳児期(0-1歳)のママの学習戦略
この時期は夜間授乳や頻繁なお世話で、まとまった時間の確保が最も困難です。でも、短時間学習には意外とメリットがあります。
この時期の特徴と対策:
特徴 – 夜中の授乳で細切れ睡眠、昼間も抱っこや授乳で時間が読めない。体力的にもきつく、集中力が続かない時期です。
対策 – 10分学習を基本とします。スマートフォンやタブレットで学習できる教材を活用し、授乳中や抱っこ中でも片手で操作できる環境を整えます。この時期は「学習習慣の維持」が最優先で、進歩の速度は求めません。
実践例 – 夜中の授乳中にスマホでプログラミング関連の記事を読む、子どものお昼寝中に10分だけコードを書いてみる、抱っこしながら音声学習コンテンツを聞くなど。完璧を求めず、「今日も少しプログラミングに触れた」という継続感を大切にします。
幼児期前期(1-3歳)のママの学習戦略
歩き回るようになり、目が離せなくなる時期です。一方で、少しずつ一人遊びもできるようになってきます。
この時期の特徴と対策:
特徴 – 好奇心旺盛で何でも触りたがる、危険なことをしがち、でも短時間なら一人遊びも可能。昼寝の時間も比較的安定してきます。
対策 – 15-30分学習を基本とし、子どもが一人遊びに集中している隙や、お昼寝タイムを活用します。子どもが興味を持って近づいてきたら、「ママのお仕事よ」と簡単に説明して、一緒に画面を見せてあげることも。
実践例 – 朝の支度が終わった後の30分、お昼寝中の1時間のうち前半30分を学習に充てる、夕食後に子どもがテレビを見ている間の15分など。この時期から「ママの勉強時間」を子どもに理解してもらう習慣を作り始めます。
幼児期後期(3-6歳)のママの学習戦略
言葉でのコミュニケーションが取れるようになり、ルールも理解できる時期です。学習時間の確保がしやすくなります。
この時期の特徴と対策:
特徴 – 集中して遊べる時間が長くなる、お手伝いや簡単なルールを守ることができる、保育園や幼稚園に通うことが多い。
対策 – 30分-1時間学習が可能になります。子どもと「お約束」を作って、「ママが勉強している間は静かに遊ぼうね」と協力してもらいます。この時期は学習の質と量を両立できる貴重な時期です。
実践例 – 保育園に送った後の朝の1時間、子どもが習い事に行っている間、夜寝る前の読み聞かせの後の30分など。子どもに「ママは今お勉強するから、○○ちゃんはパズル(塗り絵)をしようか」と提案し、一緒に静かな時間を過ごします。
小学生以上のママの学習戦略
子どもが学校に通うようになり、自分のことをある程度できるようになる時期です。学習時間の確保が最も容易になります。
この時期の特徴と対策:
特徴 – 学校に通うことで日中の時間ができる、宿題など自分の勉強もあるので、一緒に勉強する環境を作りやすい、理論的な説明も理解できる。
対策 – 1-2時間のまとまった学習時間が確保可能です。子どもの勉強時間と合わせて「家族勉強タイム」を設けると、お互いに集中しやすい環境ができます。
実践例 – 子どもが学校に行っている午前中の2時間、子どもの宿題タイムと同じ時間帯に一緒に勉強、夜子どもが寝た後の1-2時間など。「ママも新しいことを勉強しているんだよ」と話すことで、子どもの学習意欲も刺激できます。

実践的な継続テクニック集
エラーに負けない心構え
プログラミング学習でエラーが出るのは避けられないことです。でも、エラーとの上手な付き合い方を覚えれば、挫折することなく学習を続けられます。
エラーは敵ではなく先生 – エラーメッセージは「ここを直してね」という親切なアドバイスだと考えてみてください。最初は英語で分かりにくいかもしれませんが、Google翻訳を使って日本語にすると、意外と理解できることが多いです。
エラー解決の手順 – まずはエラーメッセージをよく読む、Google検索で同じエラーを経験した人の解決法を探す、それでも分からなければメンターや学習コミュニティで質問する。この手順を覚えておけば、一人でも多くのエラーを解決できるようになります。
時間制限を設ける – エラー解決に悩む時間を「30分まで」などと制限することも大切です。子育て中は時間が貴重なので、30分悩んでも解決できない場合は、一度保留にして次の日やメンターに聞くという判断も必要です。
学習習慣の定着法
継続するためには、学習を「習慣」にしてしまうのが最も効果的です。
トリガーの設定 – 「コーヒーを淹れたら学習開始」「子どもを寝かしつけたら机に向かう」など、行動のトリガーを決めます。毎回同じきっかけで学習を始めることで、自然と習慣化されていきます。
環境の整備 – 学習環境を常に整えておくことで、「やろう」と思った時にすぐに始められます。パソコンは開きやすい場所に、教材はブックマーク、ノートとペンは手の届くところに。
小さなご褒美 – 1週間継続できたら好きなスイーツ、1ヶ月継続できたら新しい本を買うなど、小さなご褒美を設定します。ただし、ご褒美がなくても続けられる程度の小さなものにすることがポイントです。
家事・育児との効率的な両立
限られた時間を最大限活用するための工夫も重要です。
マルチタスクの活用 – 洗濯機を回している間、お米を炊いている間、子どもがテレビを見ている間など、「待ち時間」を学習時間に変えます。
家事の効率化 – 作り置きおかず、冷凍食品の活用、掃除のローテーション化など、家事を効率化して学習時間を捻出します。完璧な家事よりも、学習継続を優先する期間があってもいいんです。
優先順位の明確化 – 「今日は疲れているから、夕飯は簡単にして学習時間を確保する」「来週は子どもの行事があるから、今週多めに学習しておく」など、柔軟に優先順位を調整します。
挫折を防ぐメンタルケア
自分を責めない思考法
学習が思うように進まない時、多くのママが自分を責めてしまいます。でも、それが一番の継続の敵なんです。
比較しない – SNSで他の人の学習記録を見ると、「みんなはもっと進んでいる」と感じがちです。でも、みんなそれぞれ事情が違います。他人と比較するのではなく、過去の自分と比較してみてください。
完璧主義を手放す – 「毎日やらなきゃ」「完全に理解しなきゃ」という思考は、プレッシャーになって継続を阻害します。「やらない日があってもOK」「70%理解できたら次へ」という柔軟性を持ちましょう。
小さな進歩を認める – 「今日は10分しかできなかった」ではなく「忙しい中でも10分は学習できた」と考えます。小さな進歩も立派な成果です。
サポート体制の重要性
一人で頑張りすぎず、適切なサポートを受けることも継続の秘訣です。
家族のサポート – パートナーや家族に、学習の意義と必要なサポートを伝えましょう。理解と協力があると、学習継続がずっと楽になります。
プロのサポート – メンター制度のあるスクールや、個人指導を活用することで、効率的な学習ができます。「お金をかけるのはもったいない」と思うかもしれませんが、挫折して時間を無駄にするよりも、確実に継続できる環境に投資する方が結果的にコストパフォーマンスが良いことが多いです。
コミュニティのサポート – 同じような境遇の学習仲間がいると、励まし合いながら継続できます。オンライン、オフライン問わず、自分に合ったコミュニティを見つけてみてください。
まとめ:継続は力なり、小さな一歩が大きな変化を生む
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
子育てをしながらプログラミング学習を継続するのは、決して簡単なことではありません。でも、無理のない方法で少しずつ続けていけば、必ず前に進むことができます。
大切なポイントを振り返ると:
完璧を求めない – 毎日できなくても、理解が完璧でなくても大丈夫。継続することが何より重要です。
小さな時間を活用する – 15分の積み重ねが、やがて大きな成果につながります。
一人で抱え込まない – 家族、メンター、学習仲間など、周囲のサポートを積極的に活用しましょう。
挫折も成長の一部 – 一時停止は失敗ではありません。また始めればいいんです。
子どもの成長と共に調整 – 学習方法は固定せず、生活の変化に合わせて柔軟に調整していきましょう。
私たち子育て中のママには、マルチタスク能力、問題解決力、忍耐力など、プログラミングに必要な能力がすでに備わっています。あとは、それを新しい分野で活かしていくだけです。
もし今、学習が思うように進まずに悩んでいるなら、この記事で紹介した方法を一つでも試してみてください。そして、テックアカデミーのような理解のあるスクールのサポートも検討してみてください。
一人で頑張らなくても大丈夫。みんなで一緒に、子育てしながらでも新しいスキルを身につけていきましょう。
あなたの小さな一歩が、きっと大きな変化につながります。
関連記事: